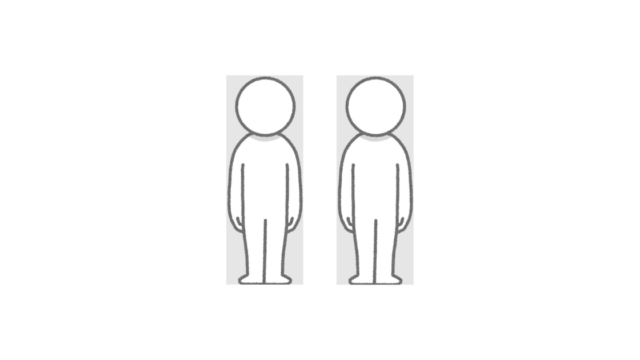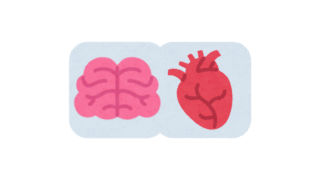本記事は対人関係に悩みを抱える人が現状を見つめなおし、対人関係の課題に取り組むきっかけをつかむことを目的にお送りしています。
現場の看護師から受ける相談や、私が経験した事例をもとに一緒に考えていきます。
今回のテーマは、「人は変えられるのか」です。
人は変えられない?
「人は変えられるのか」、対人関係に悩む人同士でしばしば議論になります。先日、私は管理職対象の研修に参加しました。そこでは「他人は変えられない、変わるのは常に自分である」と示されました。この言葉は多くの人の経験的・心理的理解を表しており、さまざまな文脈で類似の表現が見られます。
例えば、アルフレッド・アドラーは「人は過去と他人は変えられないが、未来と自分は変えられる」という言葉を残していますし、スティーブン・コヴィーは著書「7つの習慣」の中で、「影響の輪」という概念を紹介し、自分自身がコントロールできる範囲に焦点を当てることの重要性を説いています。
それでも他者を変えたくなる
この度私が受講した管理職研修の中で、「人は変えられるのか」がグループワークでも取り上げられました。参加した管理職の皆さんの多くは、どうやら「人は変えられる」と思っているようでした。
明言はされませんが「(ダメな)部下を変えるのは自分しかいない」、「育てるのが私の役割だ」と考えているように見えました。管理とは人・物・金と旧来より言われます。人と物・金を同列に扱うのはどうかとおもいますが、有名な言葉ですね。人・物・金のうち特に、「人をより良く変えていけるのが、優れた上司」とされている組織が少なくないことは否定できません。
人を変えるとはどういうことか
この思想に則って教育された管理職は、疑いなく「人は変えられる」と言います。なぜそう思うのか質問すると、「自分の指導方法で、部下は結果を出せた」とか、「職業人として成長した」などと言います。また、「若いときには反抗的だった部下が、今では自分の言うことを聞くよい部下になった」と語る人もあります。
なるほど、成績・結果を出し上司の指示に従うならば「人を変えた」と認定されるようです。
では、部下の方が良い成績や結果を残せなかったとき、上司はどう感じるのでしょうか。私が質問すると、「できの悪い部下だから。資質が足りなかった」とか「部下の努力が足りなかった」と言います。つまり部下を糾弾するわけです。
糾弾するだけでは議論が頓挫しますから、私は上司であるあなたがどう感じたかを聞きました。すると、「自分の指導方法が悪かった。自分の頑張りが足りなかった」と言います。これを聞くと、厳格で真面目な上司だと捉えられるでしょうし、多くの管理職がうなずかれるかもしれません。これらは一見正論に思えますが、果たしてそうなのでしょうか。
本当に人を変えたのか
私は、ここまで例に挙げた上司の考え方には反対です。例え上司が部下への指導を成功例と考えていても、それは「人を変えた」のではありません。部下が、ただ上司に合わせただけです。言い方を変えれば、「人が変わったように部下が振舞った」のです。
上司はこれを見て自分の手柄にしたのです。では、上司の考える失敗例はどうでしょうか。これは「部下が悪い」か「自分が悪い」と評価しているだけです。自分が悪いと言うなら謙虚に聞こえるかもしれませんが、「自分は一生懸命指導したけど、部下が応じなかった」と言っているのです。
いずれにしても関わることを諦めています。そこに「これからどうするか」という考えはありませんから、人は成長しません。
「人は変えられる」という考え方は、私は横暴だと思います。
なぜ人を変えたくなるのか
いかなる時でも変わったのはその人個人であり、上司が変えたのではありません。「人を変えられる」という考え方は、諸刃の剣でもあります。自分が優れているから人を変えられるという思考ですから、人を変えられたと感じれば人は快感を覚えます。
なにしろ自分の影響で自分の思うとおりに人を変えたのですから、気持ちよくないはずがありません。承認欲求が強烈に刺激され、枯渇した自分の心が満たされたと勘違いできます。一度この味を知ってしまうと、止められなくなります。
こうして関わる人すべてを変えたくなるのです。
承認欲求に支配されるな
大変困るのは、それを求める部下も一定数存在することです。
自分を押し殺して上司に合わせるのは本来苦痛なはずですが、合わせていれば波風は立ちません。嫌われることはなくなりますし、もしかしたら特別に扱われるかもしれません。職務上の利益を享受することもできます。こうして、不健全な需要と供給がマッチしてしまうのです。承認欲求の奪い合いです。
ただ、この承認欲求には際限がありません。もしかしたら需要と供給のつり合いが取れることもあるかもしれませんが、ごく些細なことで関係は破綻します。際限のない承認欲求を部下に求め続け、それに部下が応え続ける。もちろんその逆も起こります。それは果たして健全な組織、対人関係でしょうか。
このような関係に陥らないためには、「人を変えよう」と思わないことです。相手といくら上手くいかないとしても、です。そもそも、人を変えることはできません。これを知る必要があります。「人を変える」と決意し意気込んだとき、人はすでに他人に過干渉しています。
課題を分離する
人は原則、自分の考えで行動するしかないのです。人生は自分のものなのだから当然なのですが、これを思い違いしている人は多いです。過干渉されてはいけないし、してもいけないのです。アドラー心理学(個人心理学)では、これを課題の分離と言います。「人を変えよう」という思考は課題の分離ができていないのです。
尚、課題の分離とは「それは誰の課題なのか」を指します。それは、最終的に誰がその責任を引き受けなければならないか、を考えればわかります。他者の課題に踏み込んで不健全な共依存を作っていては、人は自立できません。他者が変わるか否かは、他者の課題です。
教育とは
上司は部下を教育する役割があります。それは否定しません。ですが、言いなりになる人を作るのは教育とは言いません。
教育とは、自分で考え自分で判断し行動できる人を育てることです。言い換えれば、自立した人を育てることです。自立した人は上司の言いなりにはなりません。上司の言い分に賛成なら部下は行動してくださるかもしれませんが、反対なら反論されます。あなたは、こんな部下を疎ましく思うでしょうか。
私はこれほど頼もしい人はいないと感じます。上司も当然、判断を間違うことはあります。適切な判断ができず、誤った指示を出します。そんな時、意見をしてくださるのです。自分に面と向かって反論・意見してくれる部下がいるのなら、喜ばしいことではないでしょうか。
これからどうするか
もし反論を受けたのなら、自分と部下の思いの何が違うのか考えてみてください。
相手が何を伝えたいのか、全身で聴いてみるのです。いくら時間がかかっても聴くのです。そして相手が本当に話し終えたら、自分の考えを表明していいでしょう。その頃には互いの意見の相違と、共通点が見えてくるはずです。
「あなたと私は意見が違いますね。では、これからどうしましょうか」という対話ができます。そんな二人であれば目標に向かって協働できる、私はそう思います。
「そんなことはない!関わっていたら相手が変わって、以前より良い関係になったことはある」と感じたひともあるでしょう。それもおそらく相手が変わったのではありません。関係を良くしようと自分が変わったのです。結果的に相手も変わったから、関係も良くなったのです。
自分が変われば、結果的に相手も変わらざるを得ません。相手を変えようとしてはなりませんが、自分が変わることによって相手も自然に変わることはあり得ます。こうした変化が起こるとき、きっとあなたと相手は対等な対人関係を築けているのです。
おわりに
「人は変えられるのか」をテーマに考えてきました。私は人を変えることはできないと考えますし、人を変えようとしてはいけないと思います。
私たちにできるのは常に自分が変わることです。
あなたはどう考えますか。
この記事に登場する人物・事例・団体などはすべて架空のものです。筆者の所属施設・関連施設とは一切の関係はありません。プライバシーに配慮して、実際の事例をもとに内容を構成したものを掲載しています。